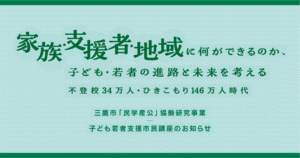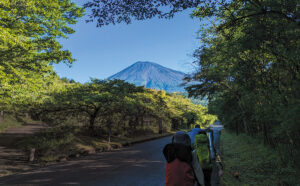【協同ネット通信 No.78 ①報告】フリースクールコスモ高等部の「現在地」〜「プロジェクト」と「講座」それぞれの取り組みから〜
※この記事は、当団体が発行している広報誌「協同ネット通信」No.78(2022年秋号)に掲載された内容をWeb用に再編集したものです。
今年度より三鷹の協同ネット本部に拠点を構えたフリースクールコスモ高等部。4月に新しいメンバーも増え、日常の積み重ねを通して、コスモ高等部という場の文化が少しずつつくられている。その「現在地」として、二つの取り組み─「広島プロジェクト」と「デザイン講座」─を取りあげ、その過程を報告する。
広島プロジェクト、始動
毎週火曜日の広島ミーティング
始まりは、「高校生としての最後の年どうしたい?」という会話。「修学旅行みたいなものはやってみたい」「広島は高校生ぐらいのうちに行くべきだと思っている」という声をきっかけに、広島スタディーツアーの企画が立ちあがった。現在のところ、五人のメンバーと12月に広島訪問予定である。
8月から事前学習の機会をもち、9月からメンバーたちと週一回のミーティングを重ねてきた。しかし、当初は参加者がなかなか揃わず、二人だけの日もあった。あるメンバーは「それぞれ来れるかどうかは個人の判断で自由だと思うけど、さすがに二人じゃ決められないし、じゃあ絶対来いとも言えないし。」と想いを言葉にした。今年度からコスモ高等部に参加しているメンバーやこの活動で初めて会ったメンバーもいる中で、日常のルーティンや想いを伝えあえる関係性がまだ前提にはなっていない。その中で、行きたいという気持ちをどう形にしていくのか、そのために想いをどう言葉にして伝えあっていくのか、毎週火曜日のミーティングという場が大きな意味を持ち始めた。
「場をともにつくる」という感覚
10月中旬、宿泊や長距離移動の不安も表明されてきたことから、当初の出発予定を延ばし、ニローネ一泊合宿というステップを踏むことにした。
広島参加予定の五人が参加し、三食ご飯をつくり、農場を見学し、夜にはミーティングを行った。帰ってきて、メンバー同士のやり取りの中で「なんかやろうよ」と声があがったり、一か所で展開されている話にだんだん集まってきたり、目でみてわかる変化もある。たった一泊であったが、生活をともにするという体験の中で、顔が向き合う、体が向き合う、場を囲む、そのような「ともにつくる」という身体感覚(?)がメンバーたちの中に生まれているように感じる。

「戦争について学ぶことは重い。でもどうして知らなきゃって思うんだろう。」

ニローネでの夜、広島に向けたミーティングが行われた。これまでも、戦争や原爆の悲惨さに触れることの「重さ」が話題になっていたが、「それでも知っておかなきゃ、広島に行って学ぼうって気持ちが生まれるのは何なんだろう」という一人の発言から話が広がった。ウクライナで起きていること…自然災害の被害…残酷なもの、怖いものを観ると「ちゃんとショック」なのに観ようと思う、観てしまうんだという想いは、メンバーたちの間で共感とともに受け止められ、「〜はどう思う?」と相互応答が始まっていった。そこには、自分たちが生きているこの世界において、ただちには理解できない・受け入れがたいものとどう向き合っていくのか、という大事なテーマがあるようにも感じる。
実際に、事前学習でドキュメンタリー番組『映像の世紀』を見たが、それは「重たい」し、「ちゃんと傷つく」ものであった。広島で起きたことは知っておくべきなんだと感じているから集まっている。ただ、今の自分にどこまで受け止められるか、どう向き合えるか、そこを自分なりに模索しているのがメンバーたちの「現在地」だろう。そこには、これまでの学校体験の中で、「みんなで」「一斉に」行われてきた平和学習への違和感や抵抗感もあるのかもしれない。対象との距離を、それぞれが近づけたり遠ざけたりしながらつかんでいく過程は大事にしたい。
出発まで残り一ヶ月。自分たちは広島で何を見てくるのか、スケジュールに落とし込んでいく必要がある。その段階では、「自分はこうしたい」という個人の視点から、「自分たちはどうするのか」という他者との共同の視点に立っていく場面も生まれてくるだろう。さらに、スタッフとしては、「ここは見てほしい、考えてほしい」という「願い」や「メッセージ」をどう伝えていくのか、自分たちが経験してきた平和学習も問いなおしながら中身づくりに取り組むことが求められている。
「働くことを学ぶ場」の活用
デザイン講座という新しい試み
今年度の活動の「軸」として、もう一つ取り組んでいるのが、協同ネットが運営してきた「働きながら働くことを学ぶ場」の活用である。昨年度はコミュニティ・ベーカリー「風のすみか」を拠点にした販売プロジェクトが展開され、今年度はデザインや組版を仕事にする「DTPユースラボ」のスタッフによるデザイン講座を実施している。前期の講座は、「レタリング」がテーマ。選んだ基本書体に合わせて自分の姓名をフリーハンドで書き起こしていく作業に取り組んだ。全9回の講座には、コスモ高等部だけでなく、コスモの10代メンバーなども合わせて五人が参加した。

メンバー自身からにじみ出てくるものを大事にしていく「余白」
DTPユースラボでは、若者の就労に向けた5ヶ月間の「集中訓練プログラム」を実施しているが、それに対して今回のコスモ高等部での講座はどのような違いがあったのだろうか。
講師の中村孝太郎さんは、「場のあり方」を挙げ、「やるべき作業はやりながら、彼ら自身からにじみ出てくるものを大事にしていく『余白』は大切にしたい」と話していた。今回の講座では、個々のペースの違いや欠席等で工程に差が出る中、「できるところまでやってみる」という形で進めていた。また、作業の合間に中村さんのこれまでの制作歴や生き方が語られたり、共通の趣味の話が広がったり(講座終了後、スピンオフ映画鑑賞会が生まれた)、その時・その場で生まれてくるものが大事にされる場であった。一方で、一定の「枠組み」に自分を合わせながら参加していくこともメンバーにとっては大事な機会でもある。講座としての「枠組み」と「余白」のバランスは今後も試行錯誤が続くだろう。
参加した一人と今後の「進路」の話をしているとき、「やりたいことって思っても特にないけど、(中村)孝太郎さんの生き方は気になる」と言っていた。高校生年代は、生き方としての「進路」を拓いていく時期であるが、限られた生活圏と一部のネットの情報の中では、「一体どう生きていったらいいの?」と戸惑い、立ちすくんでしまう。主体的な進路選択を支えていくのは、「手ざわりのある」具体的な体験であり、こうありたいという身近なモデルの存在ではないだろうか。後期に向けては、「既存のデザイン講座のような教科書的なレクチャーではもったいない。もっと根源的なものづくり、感性を培っていく体験になるといい」と中村さん。何が生まれてくるのか、私たちもワクワクしている。
10代後半の取り組みの共有化へ
こうして二つの取り組みを振り返ると、目の前のメンバーのありようや「表明」によって、私たちもときに「揺らぎ」ながら活動の展開を模索してきたと言えるだろう。10代後半という年代においては、子ども期の発達課題と青年期の発達課題が重なりあいながら表出されてくる。この年代独自の実践をどうつくっていくのか、ここで記した「現在地」を年度末に振り返り、10代後半に関わる法人内の職員と共有しながら、実践を検討していきたい。
(文・大山貴史)